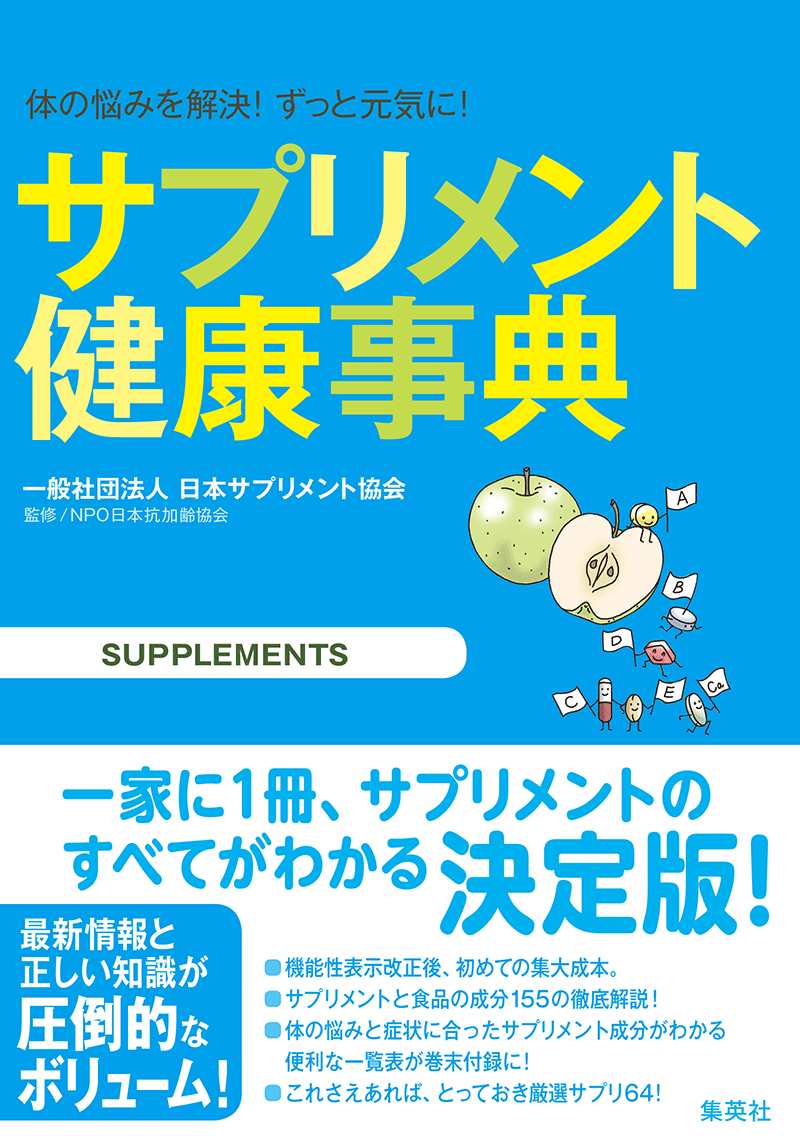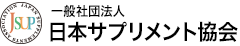- 日本サプリメント協会
- コラム
- 山野善正氏『熟成』
山野善正氏『熟成』
- 2017/11/6
- コラム
- 山野善正氏『熟成』 はコメントを受け付けていません
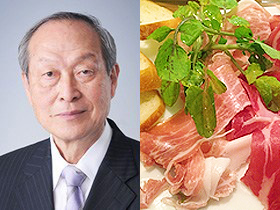
協会では、医師や専門家による鋭い視点で捉えた、健康と食に関する様々なコラムを掲載しています。今回は、一般社団法人おいしさの科学研究所理事長の山野善正氏に、「熟成」について語っていただきました。
山野 善正Yoshimasa Yamano
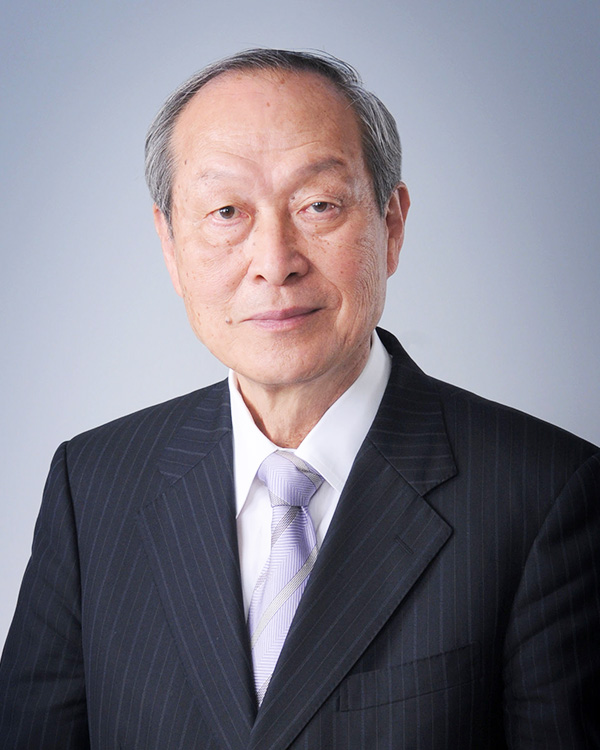 一般社団法人おいしさの科学研究所 理事長
一般社団法人おいしさの科学研究所 理事長
滋賀県生まれ。京都大学農学部農芸化学科卒業、農学博士。
東洋製缶東洋鋼鈑綜合研究所研究員を経て、香川大学農学部食品学科講師、助教授、教授。評議員、学生部長、農学部長。退職後2005年より現職。この間、アメリカ、オランダ、オーストラリアの大学で研究。専門は食品物理学。フィルム包装食品の加熱殺菌、食品コロイド、エマルション、テクスチャーについて研究。テクスチャーの研究で、食品科学工学会賞受賞。食品企業、化粧品企業等の顧問、種々の公的委員を歴任。また、民間時代レトルトパウチ第1号“崎陽軒のパック入りシュウマイ”の開発を担当。著編書にコロイド、テクスチャー関連専門書の他に、「おいしさの科学(編著)」(朝倉書店)、「おいしさの科学事典(編著)」(朝倉書店)、「おいしさの科学がよーくわかる本」(秀和システム)、「うどん王国さぬきのおいしさ」(おいしさの科学研究所)等がある。
「熟成」
熟年とか熟女とか、熟の字は人間では大人の世界の表現に用いられるが、食品の世界では熟成という用語に表れる。そして、洋の東西を問わず「熟成させた」という言葉がよく使われる。
そこで、日本語の熟成について辞書で調べてみた。まず、日本語大辞典(講談社、1989)では、
- 十分に時間をかけて望ましい状態にすること。maturing, aging
- 食品が適当な条件で一定期間貯蔵され、その間に微生物などの作用で成分が適度に変化し、独特の風味を持つようになること。ripen
また、広辞苑第2版第5刷(岩波書店、1971)では、
- 熟して十分に出来上がること。
- {化} 物質を適当な温度に長時間放置して、その間に徐々に発酵、コロイド粒子の生成そのほかの化学的変化などを行わせること。時効。
- 動物体のタンパク質、脂肪、グリコーゲンなどが、酵素や微生物の作用により腐敗することなく適度に分解され、特殊な香味を発すること。
とあり、前者の辞典にあるように、食品以外にも用いられるが、多くは確かに食品に対し用いられると考えられる。
熟成過程は微生物の酵素による化学変化、いわゆる発酵を伴うことが多いので、一歩間違えば腐敗になってしまう。永年食品包装技術に携わってきた石谷孝佑が成分からみた熟成現象をきれいにまとめているので、紹介する(表参照)。種々の成分が、種々の食材・食品で関係していることがわかる。しかも身近な日常の食品として摂取しており、食生活にはなくてはならない現象であることを再認識させられるのである。特に、保存食・嗜好品には深くかかわっており、西欧では、ワイン、洋酒、チーズに、そしてアジアでは、醤油、味噌など調味料にその現象を利用している。
表:食品の成分から見た「熟成」
| タンパク質の変化 | 動物タンパク質 | 畜肉、ハム、ベーコン、ソーセージ、干肉、 チーズ、アイスクリームミックス、ピータン、水産練り製品、 塩蔵品・荒巻き鮭、塩干品、くさや、塩辛、魚醤油、 かつお節、冷凍まぐろ |
| 植物タンパク質 | 小麦粉、パン生地、練り豆腐、手打ち麺類、 手延べそうめん、洋菓子(小麦粉系) |
|
| 脂質の変化 | チョコレート、カカオ、バター、マーガリン・ショートニング、 手延べそうめん |
|
| デンプン・タンパク質 | 味噌、醤油、黒酢、寺納豆・豆豉(とうち)、豆板醤、納豆 | |
| 微生物発酵による変化 | 発酵漬物(ぬかみそ、たくあん、キムチなど)、なれずし、発酵米麺 | |
| 糖類・デンプンの変化 | キャンディー、和三盆糖、吉野くずデンプン、 和菓子(米・あん系)、食酢、みりん |
|
| 還元糖とアミノ酸 低分子成分の変化 |
味噌、醤油、黒酢、豆豉、豆板醤 | |
| 発酵低分子成分 | 熟成清酒、ワイン、紹興酒、果実酒(成分抽出) | |
| 揮発性成分の変化 | ウイスキー、ブランデー、泡盛・焼酎、白酒、ラム酒 | |
| 食品組織の変化 | 果実の熟成、灰干しわかめ、昆布、凍みこんにゃく、 干し柿、熟成ニンニク |
|
| 色素の変化 | 灰干しわかめ、魚卵 | |
| 配合成分の熟れ | ソース、漬物(味噌・醤油漬け、酢漬け、からし・粕漬け)、ガム、 辛子めんたい、魚のみりん干し |
|
| 風味成分の変化 | 緑茶、中国黒茶・紅茶、昆布、魚卵・からすみ |
石谷孝佑,熟成とは何か,石黒知子・小林左絵子・金刺利恵子・相川直美・藤原美佐 編,
Νοστιμοおいしさの科学シリーズVol.2 ,エヌ・ティー・エス,p.49(2011)
近江に生まれた筆者にとっては、「フナずし」という乳酸発酵の馴れずしが思い出深い食べ物である。
(大塚薬報No.729より転載)